
【開催案内】第5回 KEIO SPORTS SDGs シンポジウム2025 ~スポーツが創る、持続可能な社会へ~
KEIO SPORTS SDGsは、慶應義塾のスポーツ・運動・身体活動を推進する専門部門と関連部門が連携する横断型プラットフォームです。自治体や企業など多様なステークホルダーと協力し、持続可能でインクルーシブなスポーツ・身体活動の促進を目指して、広範なプロジェクトに取り組んでいます。2022年度以降は、慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュートのスタートアップセンターとして活動し、2024年4月からは正式なセンターとして活動を拡大してきました。
2025年度は、4つの専門分科会を中心に、スポーツを通じた持続可能な社会づくりに向けた取り組みを強化しています。本シンポジウムでは、2024年度のKEIO SPORTS SDGsの進捗状況や具体的な取り組み事例を報告するとともに、スポーツの環境面への利益やインクルーシブな価値を再考する機会とします。さらに、各分科会からの最新のアップデートを共有し、スポーツを通じた持続可能な未来に向けて、多様なステークホルダーとの連携を深める場とします。
【チラシ】➤ダウンロードはこちらから
■日時
2025年3月15日(土)13:00~17:00(開場12:30)
■参加料
無料
先着200名 ※要Peatixでの事前登録
https://keiosportssdgs2025.peatix.com/
■プログラム
講演情報は順次更新してまいります。
シンポジウム趣旨説明
『KEIO SPORTS SDGs本年度の活動と今後の展望』

【演者】
慶應スポーツSDGsセンター センター長
スポーツ医学研究センター・大学院健康マネジメント研究科 教授 小熊 祐子
【講演概要】
2020年8月コロナ禍オンラインで始めたKEIO SPORTS SDGsシンポジウムは、今回で5回目になります。本年度からは、Keio Global Research Instituteの正式なセンターとして認められ、運営委員会等の基盤を作り、活動を強化してきました。本年度の活動を振り返るとともに、今後の展望について、共有します。
特別講演
『スポーツとSDGのその先へ』

【演者】
大学院政策・メディア研究科 教授 SFC研究所xSDG・ラボ代表 蟹江 憲史
【講演概要】
スポーツとSDGの関係についてはこれまでのKeio Sports SDGsでも議論を重ねているところでもあり、昨年の国連「未来サミット」でも言及されたところである。様々にかかわりあうこの課題であるが、SDGsのその先、つまりビヨンドSDGsの世界に行く時にはその重要性は益々重要になるように思われる。本講演では、ビヨンドSDGsについて起こりつつある議論を紹介しながら、スポーツのその中での役割を考えていきたい。
セッション①「自然と身体を動かしたくなる地域づくり ~誰一人取り残さない環境~」
『人・地域・社会とのつながりで育む「自然とアクティブになれる環境」』

【演者】
筑波大学体育系・助教 辻󠄀 大士
【講演概要】
スポーツを行うアクティブな人ほど、健康で長生きということは言うまでもありません。ただし、スポーツによる健康への価値はそれだけに留まりません。人と人とのつながりを生み出し、地域の中での助け合いを豊かにします。これは、スポーツをしている・していない、好き・嫌いを問わず、誰もがアクティブになれる社会環境の一翼を担っています。このような“つながり”は目には見えませんが、その可能性を“見える化”した実例やエビデンスを紹介します。
『子どもから高齢者の日常的な身体活動を促す都市・住宅環境とは』
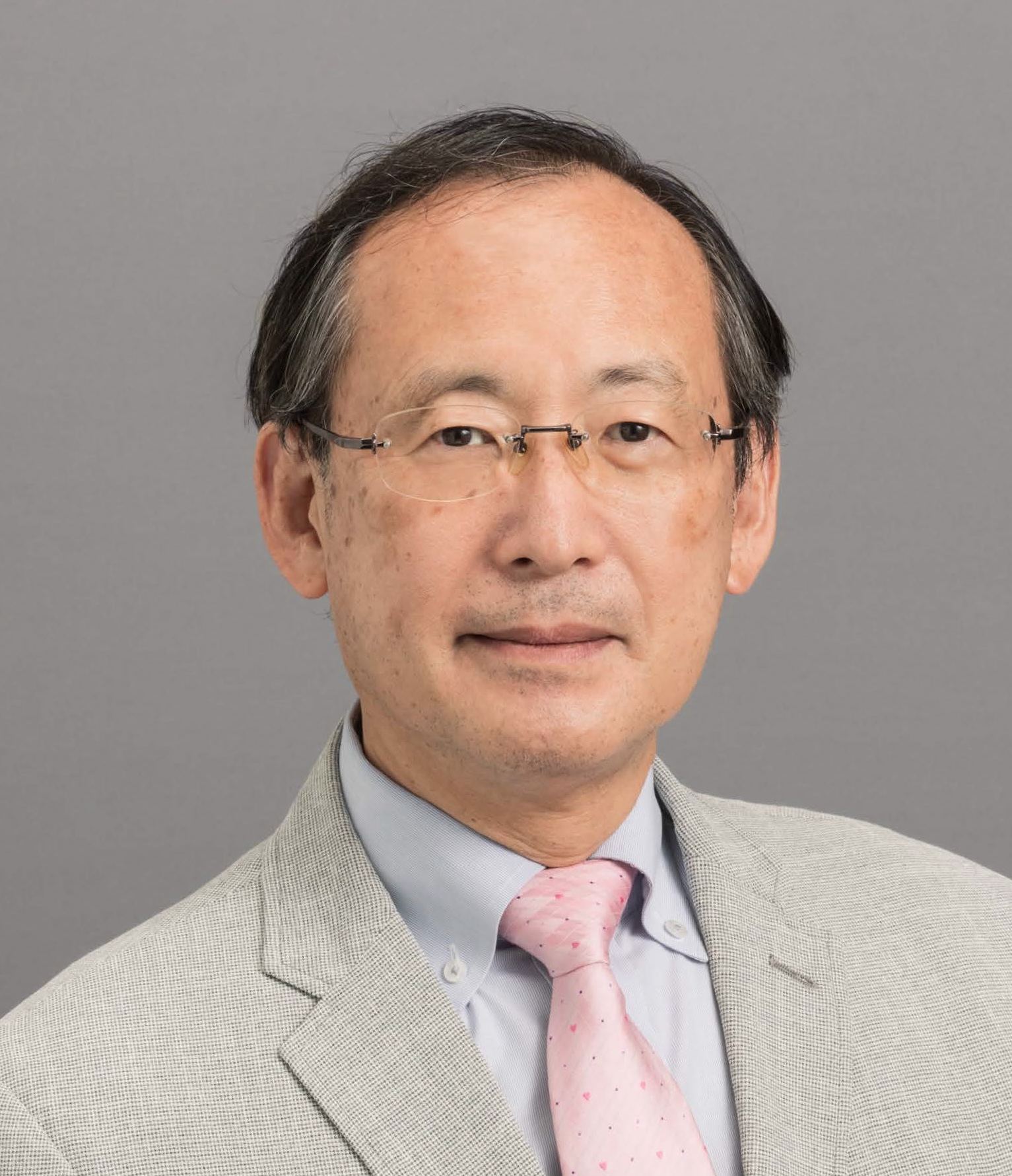
【演者】
慶應義塾大学名誉教授/一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター理事長 伊香賀 俊治
【講演概要】
幼稚園の空間・環境と園児の身体活動量・運動能力の横断・縦断調査、小学校の立地環境・施設環境と児童の身体活動量・運動能力・健康状態の横断・縦断調査、住宅の環境と高齢者の身体活動量・健康状態の横断・縦断調査の結果を紹介し、子どもから高齢者の日常的な身体活動を促し、健康を維持する望ましい都市・住宅環境を考えていただく機会にしたいと思います。
セッション②『インクルーシブスポーツ~誰一人取り残さないスポーツ~』
『2025年デフリンピックからインクルーシブスポーツの価値を考える』
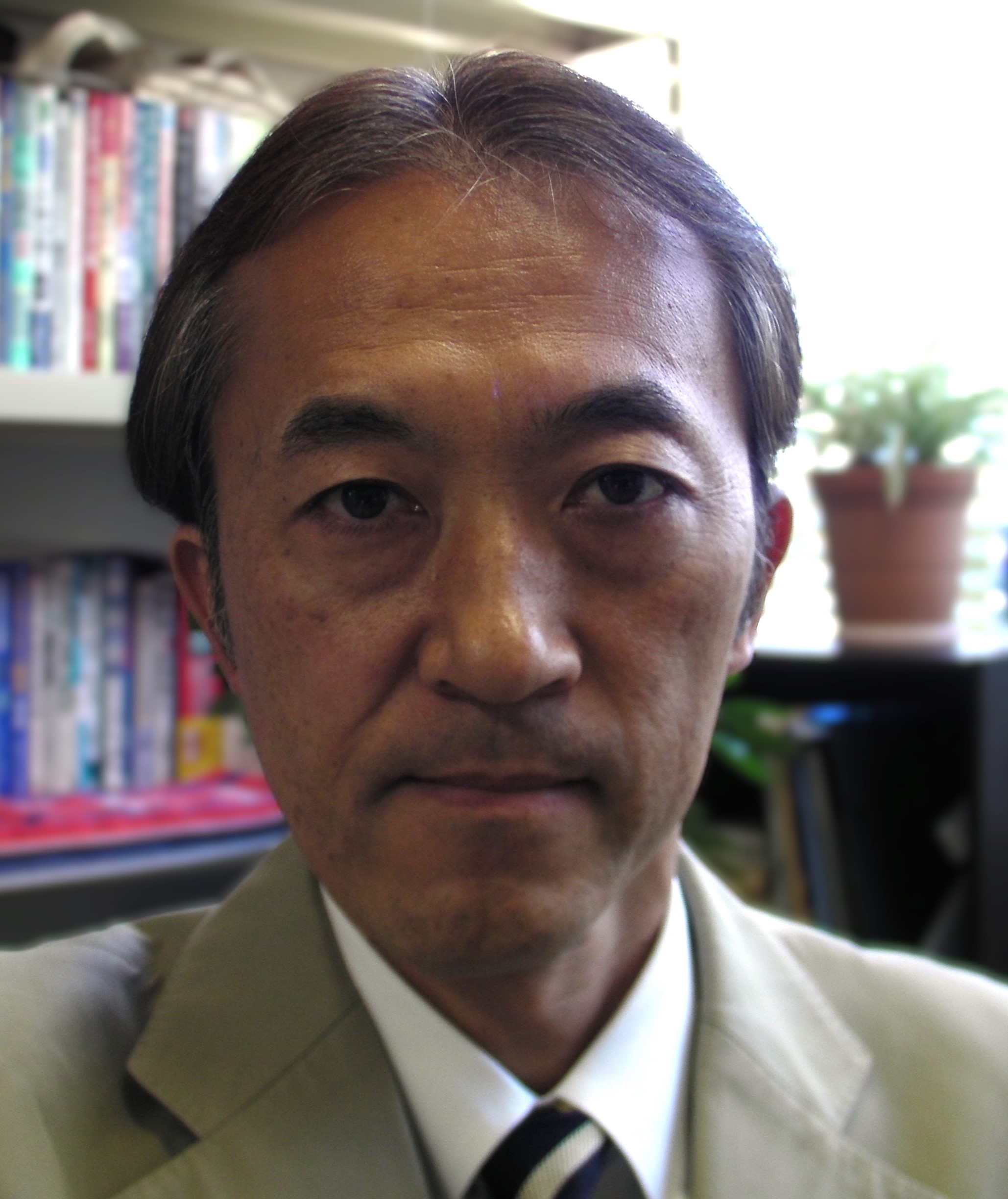
【演者】
筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター 教授 中島幸則
【講演概要】
デフリンピックとは、聞こえない、聞こえにくい人のためのオリンピックです。今年11月には、東京で100年目の記念すべき大会が開催されます。「聴覚障害者は、聞こえないだけだから、他の障害者と比べたらサポートは必要ない」、「パラリンピックと一緒にやればいい」という声も聞かれ、聴覚障害者の理解が遅れていると感じます。インクルーシブスポーツを実現させるためにも、聴覚障害者の理解、デフリンピックの存在を知っていただけたらと思います。
『パラリンピアンのサポートを通じて考えるインクルーシブスポーツ:2024パリ大会の経験から』

【演者】
日本陸上競技連盟医事委員会トレーナー部運営部員
大学院健康マネジメント研究科 公衆衛生・スポーツ健康科学専攻 後期博士課程
アスレティックトレーナー/理学療法士/JOC強化スタッフ(陸上競技、医科学) 國田 泰弘
【講演概要】
2024年パリパラリンピックでサポートを行った経験をもとに、インクルーシブスポーツについて考察します。大舞台に向けた選手と挑戦を通じて築いていく多様な側面を事例的に講演いたします。また、選手の自立を尊重しながらも必要な支援を行うアスレティックトレーナーの立場についても具体例を交え発表します。
オンライン特別講演
『Summary of presentation: Opportunities for systems approaches to promoting physical activity at the city and national level 』

【演者】
Emeritus Professor Adrian Bauman, Sydney University, Australia
【略歴】
Adrian Bauman AO, MB.BS MPH PhD DrMed (h.c, SDU) FACSM FAFPM FAHMS (Emeritus Professor of Public Health, Sydney University, Australia) has over 30 years of experience in chronic disease prevention and physical activity research. He uses epidemiological methods, as well as research methods for disease prevention and health promotion. His work has focused on helping populations to become more physically active, on surveillance to assess progress and on community-wide interventions to encourage physical activity, move more and reduce sitting time for everyone, with a focus on those who are least active. He currently co-directs the WHO Collaborating Centre on Physical Activity, Nutrition and Obesity, and contributes to in physical activity research , policy and guideline development in many countries. Current research interests include implementation science and research translation for physical activity interventions and research into physical activity policy. He is well published in the scientific literature and has been on the Clarivate list of highly cited researchers from 2014-2024.
(日本語サマリー)
Adrian Bauman AO, MB.BS MPH PhD DrMed (h.c, SDU) FACSM FAFPM FAHMS(オーストラリア、シドニー大学公衆衛生学名誉教授)は、慢性疾患予防と身体活動研究に30年以上の経験を持つ。疫学的手法に加え、疾病予防や健康増進の為の研究手法を用いる。集団がより身体的に活動的になるための支援、進捗状況を評価するためのサーベイランス、身体活動を奨励し、より多く動き、最も活動的でない人々に焦点を当てて、すべての人の座位時間を減らすための地域全体の介入に重点的に取り組んできた。現在、WHO身体活動・栄養・肥満共同センターの共同ディレクターを務め、多くの国で身体活動に関する研究、政策、ガイドライン策定に貢献している。 現在の研究テーマは、身体活動介入に関する実施科学と研究成果普及、および身体活動政策に関する研究。科学文献での発表も多く、2014年から2024年までClarivateの高被引用度研究者リストに名を連ねている。
【講演概要】
Systems thinking is becoming a popular concept in population approaches to physical activity and underpins the WHO Global Action plan on physical activity (GAPPA). The GAPPA framework combines areas of active societies, active environments, active people and active systems into an integrated approach, necessary to increase population levels of physical activity.
Systems approaches are based on research that identifies the determinants of physical activity occur within social, environmental and policy contexts. Systems are complex, and occur at municipal, regional or national levels. Approaches to working with the system involves a long time period to plan and implement programs, and building extensive partnerships across agencies, stakeholders and the community. The initial stages involve community consultation and systems mapping of physical activity linkages across sectors. This is followed by cross-sectoral planning, resourcing, and implementing action. System work often best occurs at the municipality or city-level, where the necessary partnerships and implementation approaches can occur. There are benefits for the health sector, but numerous co-benefits for other sectors, especially transport, urban planning, sport and education.
The evaluation of systems approaches may take several years, initially to monitor the implementation and reach of the PA programs, and then to demonstrate their effects on the population prevalence of physical activity.
(日本語サマリー)
システム思考は、身体活動へのポピュレーションアプローチにおいて一般的な概念となりつつあり、WHOの身体活動に関する世界行動計画(GAPPA)の基盤となっている。GAPPAの枠組みは、活動的な社会、活動的な環境、活動的な人々、活動的なシステムという分野を統合したアプローチであり、身体活動の集団レベルを向上させるために必要なものである。
システムアプローチは、身体活動の決定要因が社会的、環境的、政策的背景の 中で生じていることを明らかにする研究に基づいている。 システムは複雑であり、市町村、地域、国レベルにおいて存在する。システムに働きかけるアプローチには、プログラムを計画し実施するための長い期間と、関係機関、利害関係者、地域社会にわたる広範なパートナーシップの構築が含まれる。初期段階では、地域社会の協議と、部門を超えた身体活動の関連性のシステムマッピングが行われる。続いて、分野横断的な計画立案、資金調達、行動の実施が行われる。システムワークは、必要なパートナーシップと 実践的アプローチが可能な自治体や市レベルで行うのが最良であることが多い。保健セクターにもメリットがあるが、他のセクター、 特に交通、都市計画、スポーツ、教育などにも多くの共益がある。
システムアプローチの評価には数年かかる場合があり、最初は身体活動(PA)プログラムの実施と到達度をモニターし、その後、身体活動の人口普及率に対す る効果を実証する。
■主催
慶應義塾大学
担当:KGRI 慶應スポーツSDGsセンター スポーツ医学研究センター 大学院健康マネジメント研究科
大学院システムデザイン・マネジメント研究科 体育研究所 SFC研究所 xSDG・ラボ 医学部 スポーツ医学総合センター グローバルリサーチインスティテュート
■後援(予定)
スポーツ庁 厚生労働省 神奈川県 横浜市にぎわいスポーツ文化局 横浜市スポーツ協会
健康・体力づくり事業財団 笹川スポーツ財団 日本健康運動指導士会 慶應ラグビー倶楽部
神奈川県立産業技術総合研究所
